
朝ドラ「おひさま」と両親の戦争体験
父の郷里と「にあんちゃん」
戦時中の逸話ではないが、父の郷里である佐賀県肥前町の、昭和20年代後半のエピソードとして忘れてはならないのが「にあんちゃん」という児童文学である。
「にあんちゃん」は、昭和28年、入野村の大鶴炭鉱を舞台とした、当時10歳だった安本末子さんの書いた日記を書籍化にしたものである。
日記を読んだ長男が感銘を受け、昭和33年に出版するや大ベストセラーとなった。そして昭和34年には今村昌平監督の手により日活から映画化される。
現在、40代後半から上の世代の方であれば、小中学校の課題図書として読まれた方も多いのではないだろうか。
「にあんちゃん」はこれまでに複数の出版社から度々、再販されているが、その中の一つ、角川文庫の裏表紙にはこのような紹介文が書かれている。
*****
昭和28年、九州の炭鉱町。幼くして両親を亡くし、長男の僅かな稼ぎで身を寄せ合って暮す4人の兄妹。やがて臨時雇いの長男が解雇され、一家は離散、次兄(にあんちゃん)と10歳の末子は、知人宅の居候の身となった。さらに襲ってくる苦境に次ぐ苦境。しかし、末子は希望を捨てず、真直ぐに生きていく。貧困の苦しみ、兄妹の愛と絆、教室の友情・・・末子を取り巻く現実をありのままにつづり、日本中の涙を誘った少女日記。
*****
「にあんちゃん」には、父の生まれ育った馴染みの場所や交流のあった人物が随所に登場する。もちろん父の里帰りに同行した私にとっても馴染みの場所ということになる。
もともと小学生の日記なので大人の登場人物は少ない。故に父の知人が主要な構成人物として登場しているような、そんな印象さえ受けてしまう。
父は昭和28年3月まで肥前町の仮屋小学校で教員をしていた。その後、父は佐賀大の教育学部に進むのだが、父の進路如何では、父が登場しても不思議ではなかった。それほど生活圏に密着した物語となっている。
 父の生まれ育った仮屋集落の本家跡地に立ち、仮屋湾の対岸を眺めると、現在では巨大な風力発電の風車が回っているのが見える。写真の右手、仮屋湾の小島の島影になるかならないか、という位置に「にあんちゃん」の舞台となった大鶴集落が見える。父の話では、大鶴炭鉱全盛期には仮屋から不夜城のように炭鉱の明りが見えていたという。
父の生まれ育った仮屋集落の本家跡地に立ち、仮屋湾の対岸を眺めると、現在では巨大な風力発電の風車が回っているのが見える。写真の右手、仮屋湾の小島の島影になるかならないか、という位置に「にあんちゃん」の舞台となった大鶴集落が見える。父の話では、大鶴炭鉱全盛期には仮屋から不夜城のように炭鉱の明りが見えていたという。
それでは、「にあんちゃん」の中から父に由縁のある部分を挙げてみよう。(角川文庫 や47-1)
昭和28年4月6日(月) P33
きょうから、四年生です。しき(式)がおわってから、わかい男の先生につれられて四年三組の教室にはいりました。
(中略)
先生の名前もおしえてくださいました。滝本先生です。
→末子さんが4年の時の担任が滝本先生である。父の同僚ではなかったが、滝本さんは後に出てくる入野西の石河(イシコ)医院に度々訪れていたようだ。
石河医院は父の従姉が嫁いだ先だった。両親を早くに亡くした父は、学生時代、頻繁に石河医院を訪れている。。父はその時、何度か滝本さんに会ったという。
また、祖母が(父の母)が入野小学校で教鞭を取っていた当時、滝本さんのお父さんが同僚?だったらしい。父の話では滝本さんは東京に出て警察官になりたいと語ったらしいのだが・・・。
昭和28年5月3日(日) P39~40
ねえさんと、はじめて、のうさざきへ つわ(つわぶき)をとりに行きました。
ねえさんから、「ねずみ岩」と「わくど岩」を、おしえていただきました。「わくど岩」というのは、ほんとうに、わくど(がまがえる)がすわっているようなかっこうをしていました。
 →納所崎は仮屋湾の出口西側の岬で、対岸の仮屋側に「わくど岩」がある。父は「わくど瀬」と言っていた。
→納所崎は仮屋湾の出口西側の岬で、対岸の仮屋側に「わくど岩」がある。父は「わくど瀬」と言っていた。
父にとって「わくど瀬」は小学生の頃に船で渡り、みんなで潜ってサザエ等を捕った想い出の場所だとか。仮屋から値賀に向う大薗附近の旧道から、一瞬見ることができる。
私も小学生の頃、仮屋を訪れた際に父から説明を受けた想い出がある。それにしても、“わくど”が、ガマ蛙の意味とは知らなかったが、なるほどそっくりである。
昭和28年5月21日(木) P44
兄さんが、しごとから帰ってきて、「寺浦に行こうかね、行くまいかね」といっていました。
(中略)
兄さんは、寺浦のおすわさんまいりに行こうかね、といっているのです。
→おすわ神社(寺浦の諏訪神社)、「にあんちゃん」にも書かれている通り、マムシ除けの伝承がある。
昭和28年6月20日(土) P67~68
にあんちゃんは、六月十八日に、増本先生に日記を見せて、ほうびに五十五円の「NOTE BOOK」をもらってきて、とてもよろこんでいました。
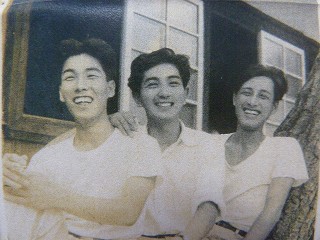 →増本昭三先生。父の仮屋小学校時代の同僚である。
→増本昭三先生。父の仮屋小学校時代の同僚である。
昭和24年度から2年間一緒に働いたそうだ。
昭和26年4月には増本さんから、入野小学校大鶴分教場に転任したことを知らせる手紙が、祖母(父の母)宛てに届いている。この移動が結果として増本さんが「にあんちゃん」に登場するきっかけとなった。祖母は以前に入野小学校でも教鞭を取っていたらしく、その何らかの関係で、増本さんは父のみならず祖母とも交流があったようだ。
またP113には滝本先生と共に増本先生の記述もある。
昭和28年10月17日(土) P113
三時ごろ、下の町内で、かくれんぼをしていて、あき家から顔を出して、ぎくっとしました。滝本先生と増本先生が、私の家の前にいるのです。
(中略)
私は、月曜日から、学校へ行けるようになったのです。滝本先生は、「本は、学校の方で、なんとかしますから、学校へやらせてください」といって、たのまれたそうです。
増本先生は、なぜこられたかというと にあんちゃんの修学りょこうのことで、こられたのだそうです。そして、にあんちゃんも、修学りょこうに、行けるようになったといわれました。
私は、あさってから、学校へ行けるのだと思うと、うれしくて、うれしくてたまりません。
→この当時、家が貧しく小学校ですら行けない子供たちが居た・・・それを教師や周囲がサポートし、学校に行かせていたことが うかがい知れる一文だ。
滝本先生は、末子さんの作文「滝本先生」で「女すけべ」と表現されるなど、かなりボロカスに書かれている・・・。確かに気分屋で怒りっぽく、生徒に腹が立つと授業もほっちらかしで自習をさせていたのは事実のようだ。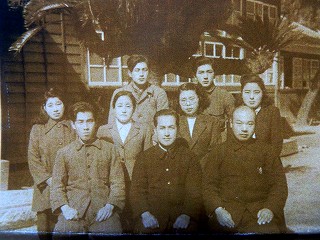 また、村の中では、良家の娘をひいきし、貧乏な家の子供は無視しているという風にも見られていたとも取れる。
また、村の中では、良家の娘をひいきし、貧乏な家の子供は無視しているという風にも見られていたとも取れる。
しかし、末子さんの日記に感動して励ましたり、あんぱんやノートを買って与えたりするなど、一概に酷い教師では無かったようだ。
父の話では、当時の授業といえば「読書きそろばん」程度で、他は野球ばかりさせていたという。英語の授業が小学校低学年からある現在から考えれば、本当に適当な教え方だったようだ。(もっともこの地方独特の雰囲気もあったのかもしれない。)そう考えると、全国ベストセラーで「女すけべ」とまで書かれてしまった滝本先生は、その後、結構大変だったのではないか?と気の毒に思えたりもする。
昭和28年7月22日(水)) P89
ドンドンドンと、たいこの音がしたので、出てみると、なにかしらないが、ぎょうれつして、えいがかんの方に向かっていました。光子さんとふたりで、行ってみました。ぎょうれつは、高串の増田神社の夏祭りのせんでんでした。
→全国でも唯一殉職警官が祭神の神社である。明治28年、村人をコレラから守り、殉職した増田巡査を祀っている。父は流行り病を防いだお坊さんが祀られていると入っていたが勘違いである。
ちなみに高串にはアコウの木の国内北限となっているそうだ。
昭和29年5月1日(土)) P177
春の遠足です。
(中略)
行く所は、仮屋の三島神社。学校から、8キロはじゅうぶんあるそうです。
(中略)
梅崎を通って、寺浦でひと休みしました。大田橋でまたひと休みし、少し行くと、いよいよ、トンネルです。
(中略)
長さは、やく百メートルあるそうです。
(中略)
トンネルの出口、入口は、日あたりがよくないので、道がじめじめして、まだ、よくかわいていませんでした。
(中略)
三島神社は、島のようになっていて、橋をわたって行くのです。(中略)橋をわたり、島のうらがわにまわって、石のかいだんをあがると、きれいなお宮がたっていました。
 →三島神社は仮屋集落の南の外れに位置する。今では「玄海海上温泉パレア」が完成しために頑強な橋が架かり、陸続きのようにも見える。三島という名の通り、独立した島が3つあったようだ。島と島の間が干潟のようでもあり、戦後に一部を埋め立てしていると考えられ、そこに現在「パレア」が半分海に浮かぶ形で建っている。
→三島神社は仮屋集落の南の外れに位置する。今では「玄海海上温泉パレア」が完成しために頑強な橋が架かり、陸続きのようにも見える。三島という名の通り、独立した島が3つあったようだ。島と島の間が干潟のようでもあり、戦後に一部を埋め立てしていると考えられ、そこに現在「パレア」が半分海に浮かぶ形で建っている。
父の話によると、三島神社に初詣などをした記憶は無いそうだ。そもそも戦前に初詣という行事自体、記憶が無いという。
トンネルの附近は確かに日あたりが悪くいつもジメジメしていたそうだ。これは地元を知らなければ書けない記述だ。子供ながらに末子さんは素晴らしい観察力を持った人だ・・・と父は言っている。
昭和29年5月13日(木)) P187~188
三日まえに、ツベルクリンはんのうをうってから、その夜、からだがかゆくなったので、
(中略)
ようご室に行って、三村先生にたずねてみると、(中略)「先生にはわからないから、先生(いしゃ)にきいてみるから、昼休みにきなさい」とおっしゃいました。
(中略)
昼休みに行くと、「さ、行きましょう」といって、先に立たれたので、ついて行きました。校門を出て、入野西の方へむかわれます。
(中略)
そういっているうちに、病院につきました。石河(いしこ)病院です。
→いしこドクター・・・。石河医院は父の従姉が嫁いだ先で、大鶴炭鉱の専属医だったそうだ。私も高校1年の時、父の里帰りに同行した際、短時間だが立ち寄った記憶が残っている。その時は既に医院を閉められていたようだ。石の門柱の脇に大きな木が茂り、少し薄暗い院内の医療器具にはカバーがかけられていた記憶がある。
父は仮屋小学校の教員を経て、昭和28年、佐賀大教育学部に行き直している。卒業後は神戸市の教員となった。遅い大学生となった父だが、入学直後に突然、祖母(父の母)が亡くなり、帰省先を失なってしまう。長い夏休みの間、ガランとした学生寮で一人生活するのは非常に重苦しい気分だったそうだ。そこで父は、長期の休みになると、この石河医院の従姉を訪ねたり、日田の夜明発電所に勤務していた姉夫婦を訪ねたりしている。父が、映画「にあんちゃん」のロケ隊が、唐津や大鶴に来ていたのを聞いたのも、この石河の従姉からだそうだ。
ちなみに、この石河医院、入院できる様、病室が2~3部屋あったのだという。ところが田舎故、入院患者も無く、基本、病室は使われることは無かった。そこで空の病室を使って下宿をさせていたらしい。父も長期の休みのほとんどを、空きの病室で、食事付きで寝泊まりさせてもらっていた。これは本家の財産を全て石河医院の開院資金に充ててしまった父の従姉の謝罪の気持ちもあったのだという。ちなみに下宿していたのは父の唐津商業学校の先輩で、有浦中学の先生だったとのこと。
私は石河医院を訪れた際、学生時代に帰省先を失った父が、休みの間を過ごした場所だったということで、少し感慨を感じながら、使われなくなった医療器具を眺めた記憶がある。
以上、ざっと「にあんちゃん」の中で、父に由縁のある記述を挙げてみた・・・。
ちなみに当時、佐賀大では「佐賀のがばいばあちゃん」こと“徳永サノさん”がトイレ掃除を担当していた。父は、昭和28年からの4年間、校内のどこかで“おサノさん”と すれ違ったこともあったのではないだろうか・・・。
「佐賀のがばいばあちゃん」に関しては、父との接点も無く、時代も10年ほど違うので、書くべき点はないのだが、「にあんちゃん」「佐賀のがばいばあちゃん」共に、両親が生きた昭和20年代の佐賀を偲ぶことが出来る作品として、私の心の中では大きな位置を占めているのである。
【参考】
・「唐津市立入野小学校」のサイトより、「にあんちゃんに関して」